
社労士はよく様々な資格と比較されます。その中の1つに同じ独立系の資格として宅建があります。
この記事では宅建と比較してどちらがよりおすすめできるかを、それぞれの業務のメリットやデメリット等と比較しながら見ていきます。
社労士と宅建はどちらが需要あり?
宅建の需要
宅建に関しては特に不動産業界でそのニーズは高いです。
そして不動産業者は5人に1人宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
この必要性からも不動産業界では特にニーズがあります。
また、不動産に関する知識は総じて勉強する機会も少なく難しい側面もあるため、宅建の勉強をするのは自身のためにもなります。
社労士の需要
企業内社労士の強みは?
1 厚生年金の届け出等で役所等の確認を省略できる。
2 その会社の人事や労務面の実情等をよく把握できる。
3 開業社労士よりタイムリーに会社の問題を解決できる。
社労士と宅建はどちらが目指しやすい職業?
試験の難易度は?
【宅建の合格率】
直近である平成29年度の合格率は15.6%です。
【社労士の合格率】
直近である平成29年度の合格率は6.8%です。
【宅建の受験資格】
受験資格はあります。
【社労士の受験資格】
受験資格はあります。
【宅建の問題形式】
1問につき4択で出題され、計50問です。
【社労士の問題形式】
選択式と択一式があります。
選択式は4~20の語群から適当なものを選び、択一式は基本的に五肢択一で、いくつかは正誤組み合わせの選択、正誤の個数の選択となります。
選択式は8科目各5問の計40問、択一式は7科目各10問の計70問です。
【宅建の一般的な学習時間】
初学者の場合:300~400時間ほど
【社労士の一般的な学習時間】
初学者の場合:800~1000時間ほど
長く続けるならどちらがオススメ?安定して働きたい方に

宅建の業務は過酷?働くことのメリットとデメリット
宅建業務のメリット
1 知識を活かし賃貸契約や購入数を上げれば、大きな収入になる
2 自身で購入する場合や契約する場合にも知識を役立たせられる
宅建業務のデメリット
1 体力面や精神面で厳しい部分がある
2 大きな買い物となるためなかなか賃貸の契約や購入に結びつかないことも多い
3 収入においてハイリスクハイリターンな側面がある
長く安定して働くなら社労士!働くことのメリットとデメリット
社労士業務のメリット
1 独占業務のため、専門性が磨かれる
2 独立や講演活動など幅広く活動できる
3 他士業との交流も多く、人脈を築きやすい
社労士業務のデメリット
1 将来AIに取って代わられる可能性が大きい
2 法改正が頻繁にあるため制度が変わりやすく、混乱の原因となる
宅建業務、社労士業務をまとめると
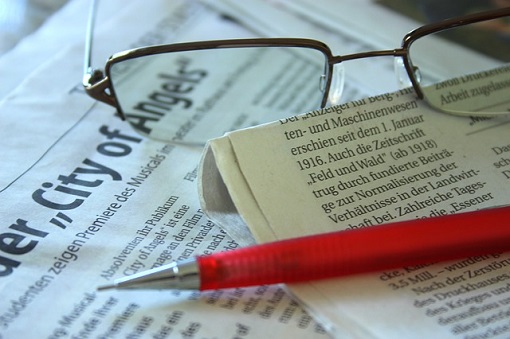
宅建業務においては収入面で大きなリターンが見込めるという大きなメリットはあります。
しかし、反面厳しい部分も少なくなく、安定という面では少し不安が残ります。
一方、社労士業務においては煩雑だったり将来AIに代わられる可能性が高いというデメリットはあります。
しかし、専門知識を活かし多角的に活躍できる場が多くあるというメリットが大きいです。
よって長く安定的に働くという意味では、宅建業務より社労士業務の方が良いということが言えるでしょう。