
社会保険科目の1つに労働保険徴収法(以下徴収法)があります。
労災保険と雇用保険をまとめて納付し徴収事務を簡略化することがこの科目の趣旨です。
この記事ではこの徴収法の難易度や出題傾向、勉強する上でのポイント等について見ていきます。
社労士試験の徴収法は難問?難易度や出題傾向を紹介
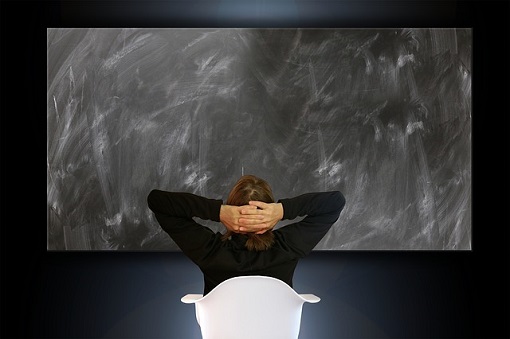
徴収法は社労士試験全体において実は最も取り組みやすい科目と言えます。
その理由として、難易度としてはあまり高くないということが挙げられます。
毎年のように繰り返し出題される論点が多くあり、勉強範囲も広くない割に問題数は6問あるので(労災、雇用とそれぞれセットで各3問ずつ出題)得点源にしやすいと言えます。
捻りのあるものや難問が出るということもほとんどなく、毎年出題される問題のレベルとしても標準的です。
更に出題分野も大体限られており、特に保険関係の成立・消滅、保険料負担、保険料申告・納付、労働保険事務組合は頻出事項です。
また選択式も出題されず、これは毎年通例で社労士の受験案内にもその旨の記載があります。
選択の勉強不要というのは択一だけに集中できるので、かなり大きな意味を持ちます。
【社労士試験】徴収法の特徴と攻略するためのポイントは?

徴収法の特徴
徴収法の特徴として、過去出題された分野や論点が繰り返し出題されるという傾向があります。
そして問題自体も基本事項をちゃんと押さえておけば得点できる標準的な問題が多いです。
また、選択も出題がないため択一対策のみでOKです。
攻略するためのポイント
徴収法の最も効果的な学習法は過去問攻略です。
過去出題された論点が繰り返し出題されるため、過去問を徹底的に押さえることが得点するための秘訣と言えます。
徴収法の中で特に難しいのはメリット制だと感じます。ここは継続事業と有期事業との違いを中心に押さえましょう。
また労働安全衛生法のように範囲が広い割には出題が少ない科目と違い、範囲が狭い割に出題数は多めなので費用対効果が高い科目とも言えます。
また労災保険法と雇用保険法とセットで出題されるので、これらが苦手でも徴収法でカバーすることもできます。
ですので、徴収法に関しては過去問を繰り返し演習し、得点源となる得意分野にしていくのが得策でしょう。
ちょっとした計算問題もありますが、複雑ではないので演習を通して慣れていきましょう。
労働保険徴収法を得点源にするためには?具体的な勉強方法を紹介
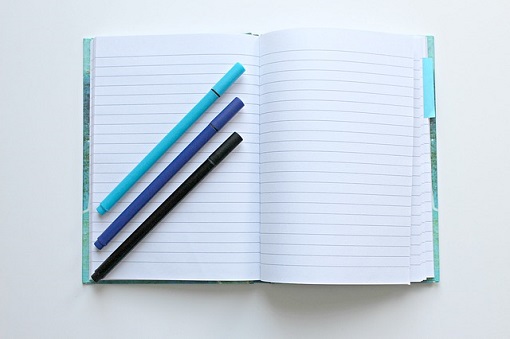
保険関係の成立・消滅
徴収法では労災保険や雇用保険が成立した時、消滅した時の要件や書類提出期限等が問われます。
例えば適用事業と暫定任意適用事業の成立・消滅はその時期を押さえる、有期事業、継続事業の一括の要件を押さえるということを主軸に学習するのが良いでしょう。
過去問等でどのように問われているのか、数字や時期等の要件も併せて確実な知識にしていきましょう。
この単元は基礎的なことをしっかり覚えていれば得点源にできる分野でもあるので、ぜひ得意分野にしてしまいましょう。
保険料負担
この単元では保険料を負担する際に欠かせない保険料率を事業の種類と共に覚えましょう。
また、保険料の種類がどれだけあるかや一般保険料が免除される高年齢労働者の年齢、納付の際の端数処理、賃金から控除する際の決まりといったことも頻出事項です。
労災保険料率と雇用保険料率の区分けもしておくましょう。
数字的な要素も少なくないので、その部分を中心に基礎的な知識を習得していきましょう。
過去問でどのように問われているか確認し、出題ポイントを把握して様々な問題に対応できるようにしていきましょう。
保険料申告・納付

徴収法の中で一番数字や計算が登場する単元です。
概算保険料の申告や延納は特にそうですが、その時期や延納回数を中心に覚えましょう。
延納は何期に分けられ、いつまでに納付するのかが最も問われるポイントです。
時期の区切りも最初は難しく感じるかもしれませんが、コツさえ掴めればさほど難しくありません。ここは重点的に押さえましょう。継続と有期の違いにも着目してください。
また、増加概算保険料や確定保険料との違いも把握しましょう。
この辺は混同しがちなので、過去問で各問題の出題のしかたはどうかを、それぞれ比較しながら確実に押さえていきましょう。
労働保険事務組合
労働保険事務組合も出題割合としては多めです。
特に組合の認可基準や委託できる業務の範囲、手続きや解除の際の要件等が頻出事項です。
これらを中心に基礎的な部分をしっかり押さえておけばそれほど苦戦することはないと思われます。
過去問等を利用して問題演習をしっかりしておけば、ここも得点源にできるはずです。
数字的な要素も他の単元に比べればさほど見受けられないので、比較的取り組みやすい単元とも言えます。